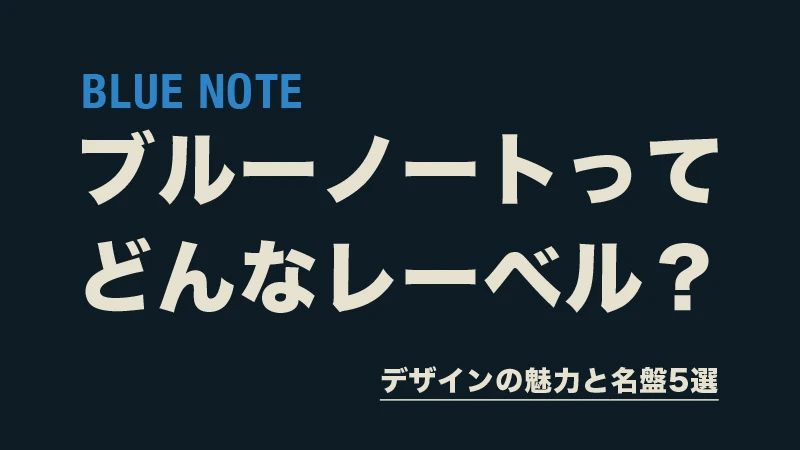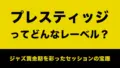どうも、ズワイガニです。
ジャズを聴いていると必ず耳にする名前、それが「ブルーノート(Blue Note)」。
アルバムのジャケットが並んでいるだけで、おしゃれに見えるのは、多くの人が感じたことがあるはずです。
今回はブルーノート・レーベルの歴史と、独特なデザインの魅力、そしておすすめの名盤5選をエピソードを交えてご紹介します。
ブルーノートとは?
ブルーノート・レコードは1939年、ニューヨークでアルフレッド・ライオンによって設立されたジャズ・レーベルです。当初は批評家で作曲家でもあったマックス・マーギュリスが資金を支援し、同年にはライオンの幼なじみで写真家のフランシス・ウルフがドイツから渡米して経営に参加しました。
記念すべき初録音は1939年1月6日、アルバート・アモンズとミード・ルクス・ルイスによるブギ・ウギ・セッション。ブルーノートはここから歴史をスタートさせます。
設立当初からブルーノートは他のレーベルと一線を画していました。
- リハーサル代の支給
- 演奏時間や選曲に大きな自由
- アーティストを対等なパートナーとして扱う姿勢
当時まだ差別や偏見が根強かった時代に、彼らは黒人ジャズ・ミュージシャンをリスペクトし、演奏に最大限の自由を与えた点で特別な存在でした。こうしたアーティスト・ファーストの方針により、ジャズ・ミュージシャンから絶大な信頼を得ることとなります。
後にセロニアス・モンク、アート・ブレイキー、ジョン・コルトレーン、ハービー・ハンコックなど、ジャズ史を動かす名演が次々とブルーノートから生まれていくのです。
ブルーノートならではのエピソード
セロニアス・モンクへの賭け
1940年代後半、まだ評価が定まらず「難解」とも言われていたセロニアス・モンクを、ライオンは早くから録音しました。
周囲が懐疑的でも、彼はモンクの独創性を信じて作品を残し、結果的に『Genius of Modern Music』という歴史的シリーズへとつながります。これはブルーノートの先見の明を示す象徴的な出来事でした。
『The Preacher』をめぐる攻防
ホレス・シルヴァーの代表曲 『The Preacher』は、実は録音前にライオンが「古臭い」として採用を渋った曲です。
しかし、ホレス・シルヴァーやアート・ブレイキーが「これをやらなければセッションを降りる」と強硬に主張。最終的に収録され、大ヒットを記録しました。
この一件は、ブルーノートがミュージシャンの声を尊重した好例として語り継がれています。
ジミー・スミスを発掘した感動
オルガン奏者ジミー・スミスを初めて聴いたとき、ライオンはその才能に衝撃を受け、すぐに録音を提案。録音後、自宅で彼の音を聴きながら「この音を世界に届けたい」と喜んでいたといいます。
ブルーノートが、音楽そのものを愛し、心から応援する人間の集まりだったことがよく分かるエピソードです。
ルディ・ヴァン・ゲルダーは眼科医エンジニア
ブルーノートの録音を支えたエンジニア、ルディ・ヴァン・ゲルダーは本職が眼科検眼士。昼は診療所で働き、夜や休日に自宅スタジオで録音をしていました。
眼科医エンジニアが残した音が、いまやジャズ録音の代名詞になっているのは面白い事実です。
フランシス・ウルフの写真が音のヴィジュアルに
共同経営者フランシス・ウルフは、レコーディング現場で常にカメラを構え、ミュージシャンの自然な表情を撮影しました。
その写真はジャケットや宣材に使われ、「音が聴こえてくる写真」とまで評されています。ブルーノートのヴィジュアル・アイデンティティを作った存在です。
録音は深夜〜早朝に
クラブでの演奏を終えたジャズマンたちは、夜遅くや早朝にスタジオへ直行して録音することもしばしば。疲れているはずなのに、むしろライブの熱気が冷めないまま収録された演奏が、名盤の数々を生み出しました。
ジャケット・デザインの魅力
ブルーノートといえば、なんといってもジャケットのデザイン性。
デザインを手がけたのはリード・マイルス。彼の仕事はモダン・ジャズの音を視覚的に翻訳したデザインといわれています。
特徴は以下の通りです。
- 太いサンセリフ体の大胆なタイポグラフィ
- モノクロ写真+ブルーやグリーンなどの差し色(2色刷り)
- フランシス・ウルフ撮影の演奏風景を活かした構図
- 余白を生かしたシンプルで力強いレイアウト
実はこうしたスタイルは印刷予算が限られていたことが背景にありました。フルカラーが使えない制約の中で、かえってモダンで洗練された美学が生まれたのです。
その結果、ブルーノートのジャケットは単なるレコードの包装を超え、グラフィック・デザインの傑作としても高く評価されています。
ブルーノートのおすすめの名盤5選
初心者にも聴きやすく、ジャケットの魅力も堪能できる名盤を5枚選びました。
Somethin’ Else / キャノンボール・アダレイ (1958)
マイルス・デイヴィスが全面参加し、オープニングの『枯れ葉』はジャズ史に残る決定的名演。キャノンボールのアルト・サックスとマイルスのミュート・トランペットが緊張感と抒情を同時に描き出し、まるで会話のようなやり取りを楽しめます。
黒地に白抜き文字と小さな写真というシンプルなデザインは、ブルーノートの余白美学を象徴しています。
Moanin’ / アート・ブレイキー & ザ・ジャズ・メッセンジャーズ (1958)
アート・ブレイキー率いるジャズ・メッセンジャーズの代表作で、ソウルフルなハード・バップの魅力が詰まった一枚。タイトル曲の掛け合いは聴く者を一気に引き込み、熱気あふれるライブ感をそのまま封じ込めています。
ブレイキーの真剣な表情を大きく切り取ったジャケットと力強いタイポグラフィが、音楽の迫力をそのまま視覚化しています。
Blue Train / ジョン・コルトレーン (1957)
コルトレーン唯一のブルーノート・リーダー作で、疾走感と深みを兼ね備えた名盤。特にタイトル曲は、硬派で力強いモダン・ジャズの象徴とされ、今も多くのファンを魅了し続けています。
ジャケットに配された青緑の色調と沈思するコルトレーンの顔は、ブルーノートを象徴するビジュアルとして世界的に知られています。
Song for My Father / ホレス・シルヴァー (1965)
ファンキー・ジャズの名手ホレス・シルヴァーが父に捧げた温かみのあるアルバム。ラテンのリズムを取り入れた表題曲は耳に残るメロディで、世代を超えて愛されています。
父親の写真を配したジャケットは、モダンなタイポグラフィと人間味のある肖像が融合した、ブルーノートならではの一枚です。
Maiden Voyage / ハービー・ハンコック (1965)
海をテーマにしたモード・ジャズの傑作で、浮遊感のあるピアノと緊張感あるアンサンブルが航海のイメージを巧みに描き出しています。実験的でありながら聴きやすく、今なお色褪せない新鮮さを持っています。
波を思わせる写真処理とブルーとグリーンの色合いが、音楽のテーマと見事に響き合っています。
おわりに
ブルーノートのレコード・ジャケットって、つい飾りたくなるんですよね。実は私の地元の小料理屋さんにも『Somethin’ Else』がさりげなく飾ってあって、思わずニヤリとしてしまいました(笑)
音楽を聴く前から「ジャズの世界」に入り込める。そんな不思議な魅力があるのも、ブルーノートならではだと思います。
まだ聴いたことがない方は、ぜひ今回ご紹介した名盤から気軽に耳を傾けてみてくださいね!