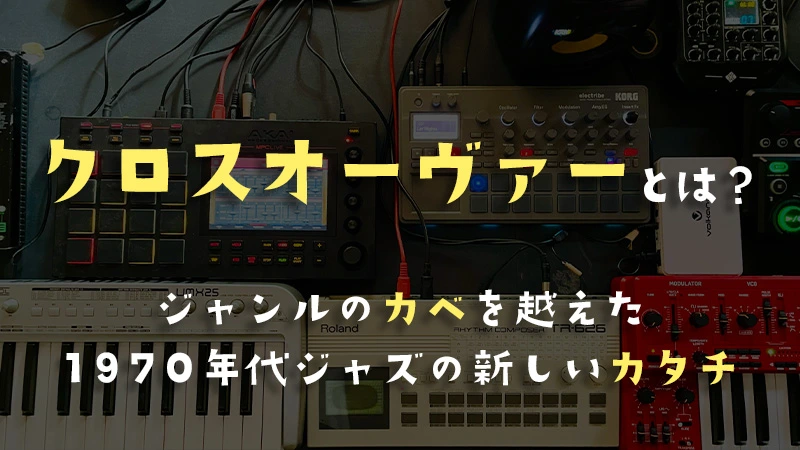どうも、ズワイガニです。
クロスオーヴァーというジャンルが一時期あったそうなんです。一時期というのはもう呼ばれなくなったからなんですけど・・・。
今回は1970年代に突如登場したジャンル、クロスオーヴァーについて、わかりやすく解説していきます!
クロスオーヴァーってなに?
クロスオーヴァー(Crossover)とは、1970年代に主に使われた音楽用語で、ジャズを軸としながらもロック、ソウル、ファンク、R&B、クラシックなど他ジャンルとの垣根を越えた融合音楽を指します。
もともと“crossover”という単語は、「交差する」「越境する」といった意味になります。ジャズ・ミュージシャンたちが、従来のスタイルにとらわれずに他ジャンルの要素を積極的に取り入れていく動きが顕著になったことで、クロスオーヴァーという言葉が登場しました。
なぜクロスオーヴァーと呼ばれたのか?
クロスオーヴァーが音楽用語として広まったのは、ラジオやレコードと並び、音楽雑誌のメディアによる言及が大きなきっかけでした。
1970年代には、“ジャズ”カテゴリだけではもはや説明しきれない作品ジャンルが登場し、その変化を指す用語として、レビューや紹介文で「クロスオーヴァー」というラベルが使われるようになったのです。
そして、音楽ジャンルとして定着した背景には以下の要因が考えられます。
ジャンル境界の曖昧さを言語化
雑誌では「ジャズ」と「ソウル」「R&B」「ロック」といった音楽の境目を越えた作品として境界を越える(cross over)という表現が的確だったこと。
マーケティング用語としての役割
ジャズ専門誌やポップス系雑誌で「このアルバムはBBチャートにも入ったよ」的な紹介がされるようになり、リスナー層が幅広いシリーズを指すキャッチコピー的な用語として定着したこと。
ジャズ批評家によるジャンル分類
即興やジャズ理論を下敷きにしつつ、ポップやR&B要素を融合した作品を指すジャンル区分として使いやすかったこと。
なぜクロスオーヴァーと呼ばれなくなったのか?
1980年代に入ると、クロスオーヴァーという呼び方は徐々に使われなくなっていきます。その理由はいくつかあります。
「フュージョン」という呼称への移行
1970年代後半から、ロックやファンクとの融合を推し進めたフュージョン(Fusion)が台頭しました。ジャズ界内でもクロスオーヴァーより具体的で広範な概念として受け入れられ、呼称が変化していきました。
スムース・ジャズへの再ラベル化
1980年代以降、さらに商業的で聴きやすいスムース・ジャズという形に進化していきます。かつてクロスオーヴァーと呼んでいた作品も、新たに「スムース・ジャズ」、「コンテンポラリー・ジャズ」と呼称されるようになりました。
批評家やファンからの評価
批評の中には「即興性が薄れた」「商業的すぎる」との批判もあり、一部のミュージシャン自身もクロスオーヴァーという言葉から距離を置くようになりました 。
クロスオーヴァー時代の名盤
クロスオーヴァー時代を象徴する代表的なアルバムを紹介します。
Head Hunters / ハービー・ハンコック(Columbia, 1973年)
ファンキーなビートとシンセサイザーが前面に出たジャズ・ファンクの金字塔。商業的にも飛躍的な成功を収め、発売からすぐにゴールド/プラチナ認定されました。ライナー・ノーツには「ジャズの目を開かせる乗り物」と讃えられ、「ファンキーなクロスオーヴァーの架け橋」と紹介されました。
![]() ブラック・ミュージックとジャズを溶け合わせた親しみやすい演奏とグルーヴで、ジャズ未経験層も広く取り込んだ先駆け的作品であるぞ。
ブラック・ミュージックとジャズを溶け合わせた親しみやすい演奏とグルーヴで、ジャズ未経験層も広く取り込んだ先駆け的作品であるぞ。
Two / ボブ・ジェイムス(CTI, 1975年)
ボブ・ジェイムスは70年代にクロスオーヴァー路線を拓いたキーボーディストです。本作はキャッチーなメロディを重視し、ポップスやR&B、クラシックからの引用をジャズで包んだ典型的なCTIサウンド。管弦ストリングスやパーカッションを大々的に使い、聴きやすい作風で、「70年代のクロスオーヴァーの定番サウンド」となっています。
![]() 特に『Take Me to the Mardi Gras』などはその後多くのサンプリングに使われ、ジャズ・ファンだけでなく幅広い層に受け入れられた代表作であるぞ。
特に『Take Me to the Mardi Gras』などはその後多くのサンプリングに使われ、ジャズ・ファンだけでなく幅広い層に受け入れられた代表作であるぞ。
Prelude / エウミール・デオダート(CTI, 1973年)
映画『2001年宇宙の旅』のテーマ曲にもなったクラシック曲『ツァラトゥストラはかく語りき』をファンキーにアレンジした楽曲で知られる一枚。ストリングスやハモンド、エレピとともにクラシック旋律を大胆に取り込み、若者にも親しみやすいサウンドに仕上げています。全米チャートで最高2位を記録し、1974年のグラミー賞最優秀ポップ・インストゥルメンタル・パフォーマンス賞も受賞する大ヒットとなり、CTI屈指の売上を記録しました。
![]() ジャズ・ファンクとクラシックの融合の先駆け的アルバムで、ヒップホップ世代にも多大な影響を与えたんじゃ。
ジャズ・ファンクとクラシックの融合の先駆け的アルバムで、ヒップホップ世代にも多大な影響を与えたんじゃ。
おわりに
「クロスオーヴァー」という言葉は、今ではあまり聞かれなくなりましたが、1970年代の音楽シーンにおいては、新しいジャズのカタチを模索した重要なキーワードでした。
ジャズという土台を持ちながら、他ジャンルとの対話によって新たな音を切り拓いたムーブメントといえます。
今でこそ「ジャンルレス」や「ミクスチャー」が当たり前のようになっていますが、その原点のひとつはこのクロスオーヴァー期にあるのかもしれませんね!