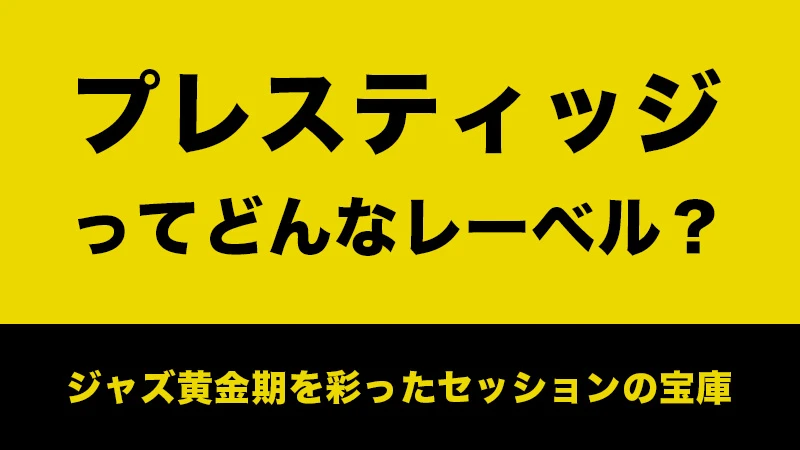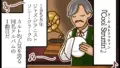どうも、ズワイガニです。
ジャズを語る上で欠かせないレーベルのひとつがプレスティッジ・レコード(Prestige Records)です。1949年にニューヨークで誕生したこのレーベルは、マイルス・デイヴィスやジョン・コルトレーン、ソニー・ロリンズといった名だたるジャズメンの傑作を世に送り出しました。
プレスティッジの魅力は、なんといっても即興性を重んじたセッション録音。ほとんどリハーサルを行わず、スタジオに集まった演奏家たちの「その瞬間のジャズ」を切り取った作品が数多く残されています。ブルーノートのように緻密に作り込むスタイルとは対照的に、ラフで生々しい空気感を残しているのが特徴です。
本記事では、そんなプレスティッジの特徴や名盤を紹介しながら、その魅力に迫っていきます!
プレスティッジとは?
プレスティッジ・レコードは、1949年にニューヨークでボブ・ワインストックによって設立されました。当初は「ニュー・ジャズ」という名前でスタートしましたが、すぐに「プレスティッジ」と改称。以降、1950〜60年代にかけて、モダン・ジャズの黄金期を記録する重要なレーベルへと成長していきます。
ブルーノートがリハーサルや編曲を重視して作品を丁寧に作り込んだのに対し、プレスティッジはセッション中心のワン・テイク主義を徹底。スタジオに集まった演奏家たちの即興性とその瞬間のスリルを切り取ることにこだわりました。
その結果、ミスや偶然のアドリブまでも含めた生のジャズがレコードに刻まれました。こうしたセッション中心のスタイルは、アーティストたちの個性や即興力を最大限に引き出すこととなり、数々の名演を残すことにつながりました。
プレスティッジの特徴
プレスティッジには、他のレーベルとは一味違う特徴があります。そのいくつかを紹介しましょう。
ワン・テイク主義
プレスティッジの録音では、基本的にリハーサルは最小限、ほぼワンテイクで進められました。「テイクを重ねると新鮮さが失われる」という考えから、演奏家の第一声がそのまま作品になることもしばしば。多少のミスも味として残す姿勢が、ジャズの生々しさを伝える要因になりました。
例えば、ソニー・ロリンズの代表作『サキソフォン・コロッサス』も、ほとんどリハーサルをせずに録られたアルバムです。一発勝負の空気感が、結果的にジャズ史に残る傑作を生み出すというのもプレスティッジらしいといえるでしょう。
ルディ・ヴァン・ゲルダーの存在
ニュージャージー州の自宅兼スタジオで録音を手がけていた名エンジニア、ルディ・ヴァン・ゲルダーも、プレスティッジに欠かせない存在です。
後にブルーノートでも活躍しますが、プレスティッジ時代にはすでに「ジャズ録音の魔術師」として知られ、透明感と臨場感のあるサウンドで数々の名盤を支えました。
契約とステップアップの舞台
プレスティッジは、若手ジャズメンの登竜門的な存在でもありました。
例えばマイルス・デイヴィスはプレスティッジで数多くの名作を残した後、コロムビアへ移籍し大きく飛躍。ジョン・コルトレーンも同様に、プレスティッジでの録音が後のブルーノートやインパルス!での活動につながっていきます。
ここで重要なのが契約条件です。プレスティッジは比較的自由に録音をさせてくれる代わりに、契約金や印税はそれほど高くなく、長期的なサポート体制も整っていませんでした。一方で、大手レーベル(コロムビアやインパルス!)は宣伝力や流通力、潤沢な予算を持っており、契約金もプレスティッジとは桁違い。演奏家にとっては、より良い待遇とキャリアの飛躍を求めてステップアップするのは自然な流れでした。
つまり、プレスティッジは「名を上げるための最初の舞台」であり、「次のステージへ羽ばたくための通過点」でもあったのです。
ボブ・ワインストックについて
プレスティッジを創設したのは、当時まだ20歳そこそこの青年、ボブ・ワインストックでした。幼い頃から熱心なレコード収集家で、やがて通信販売や「ジャズ・レコード・コーナー」という小さな店を開いたことがレーベル設立のきっかけとなります。
ワン・テイク主義はワインストックが決めた方針です。彼は「リハーサルを重ねると演奏の鮮度が失われる」と考え、最小限のリハーサルとワン・テイク主義を徹底しました。時には失敗テイクをその場で上書きしてしまうこともあり、結果としてプレスティッジ特有のラフでスリリングな音が生まれました。
また、経営者としての抜け目なさも見逃せません。マイルス・デイヴィスがコロムビアに移籍を決めた際、プレスティッジとの契約義務がまだ残っていました。ワインストックは契約の履行を求め、マイルスはこれを効率的に片付けるためにわずか2日間でアルバム4枚分を録音。その音源は『Cookin’』『Relaxin’』『Workin’』『Steamin’』としてリリース。したたかな経営判断でありながら、結果的に名盤を生むことになった有名なエピソードです。
さらに、プレスティッジの運営方針は常に倹約的でした。リハーサル代やスタジオ費用も最小限に抑えられ、年間70以上のセッションをこなす多作体制で進められました。そのため、細かな作り込みよりも演奏の勢いとスピード感を優先するスタイルが確立したのです。
1972年にプレスティッジをファンタジー・レコードに売却したのち、ワインストックは音楽業界を離れて投資の世界に転身。晩年はフロリダで暮らし、2006年にその生涯を閉じました。
プレスティッジのおすすめの名盤5選
プレスティッジからは、数えきれないほどの名盤が生まれました。その中でもジャズ史を語る上で外せない作品をいくつか紹介します。
ウォーキン / マイルス・デイヴィス (1954)
ハード・バップの幕開けを告げた記念碑的アルバム。力強いホーン・セクションとブルース感あふれる演奏は、以降のジャズの方向性を決定づけました。
サキソフォン・コロッサス / ソニー・ロリンズ (1956)
ソニー・ロリンズの代表作にして、ジャズ・サックスの金字塔。『セント・トーマス』『モリタート』など名演揃いで、プレスティッジを象徴する1枚。
ソウルトレーン / ジョン・コルトレーン (1958)
プレスティッジ時代のジョン・コルトレーンを代表するアルバム。彼のシーツ・オブ・サウンド奏法が全開で、後のインパルス! 時代への萌芽が感じられます。
バグス・グルーヴ / マイルス・デイヴィス (1954)
マイルス・デイヴィス、セロニアス・モンク、ミルト・ジャクソンら豪華メンバーが集結したセッション。ラフな録音ながら、即興のスリルが凝縮されています。

テナー・マッドネス / ソニー・ロリンズ (1956)
ジョン・コルトレーンとの唯一の共演が記録された貴重なアルバム。二人のサックスの火花散る応酬は、プレスティッジらしい即興性の象徴ともいえる名演です。
おわりに
プレスティッジ・レコードは、1949年の設立以来、ジャズの生の瞬間を切り取ることに徹したレーベルでした。ワン・テイク主義によるラフで即興的な録音は、時にミスさえも作品に刻み込み、その結果としてジャズという音楽の本質を鮮やかに残すことになりました。
ここから生まれた名盤たちは、今もジャズ史に輝く金字塔です。さらに『テナー・マッドネス』のように、二度と実現しなかった豪華共演を記録した作品も少なくありません。
ジャズの即興らしいラフさやスリルを楽しみたいなら、まずはプレスティッジの名盤を一枚聴いてみてください。きっと「これがジャズだ!」という生の空気を感じられるはずです!