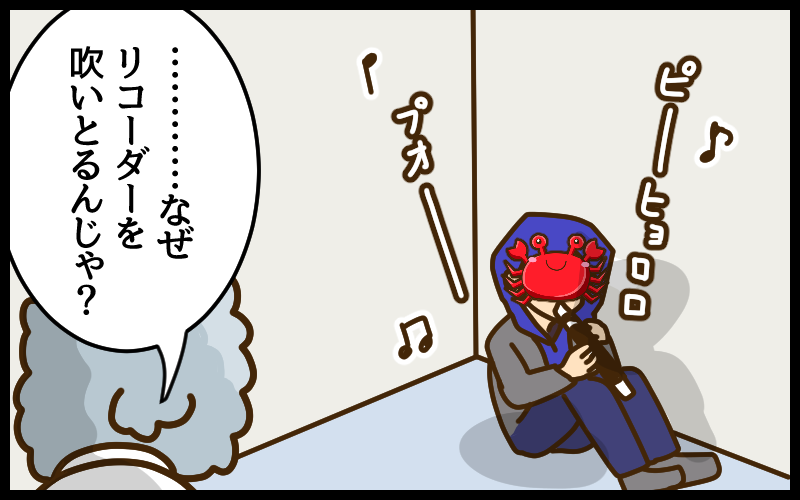どうも、ズワイガニです。
リコーダーと聞くと、多くの人は小学校の音楽の授業で使った楽器を思い浮かべるでしょう。
しかし、リコーダーは単なる学習用の楽器ではなく、歴史ある奥深い楽器なんです。種類も音域によって小さいものからとんでもなく大きいものまであるんです。
この記事では、そんな奥が深いリコーダーについて掘り下げていきたいと思います!
にわかジャズファン。この記事のライター。ハンドル・ネームを安易に付けてしまったため、蟹のお面を付けたキャラになってしまった。
![]() しったかJAZZ博士
しったかJAZZ博士
しったかジャズファン。このブログの解説役である博士。時に毒舌、時におとぼけ。知ったかのくせに。
【4コマ漫画】ピューと吹く!ズワイガニ

はじめに
![]() というわけで、今回はリコーダーを紹介させていただきます!
というわけで、今回はリコーダーを紹介させていただきます!
![]() リコーダーの記事じゃが、本当にそんなに読まれとったんか?おおん?
リコーダーの記事じゃが、本当にそんなに読まれとったんか?おおん?
![]() ほい。
ほい。
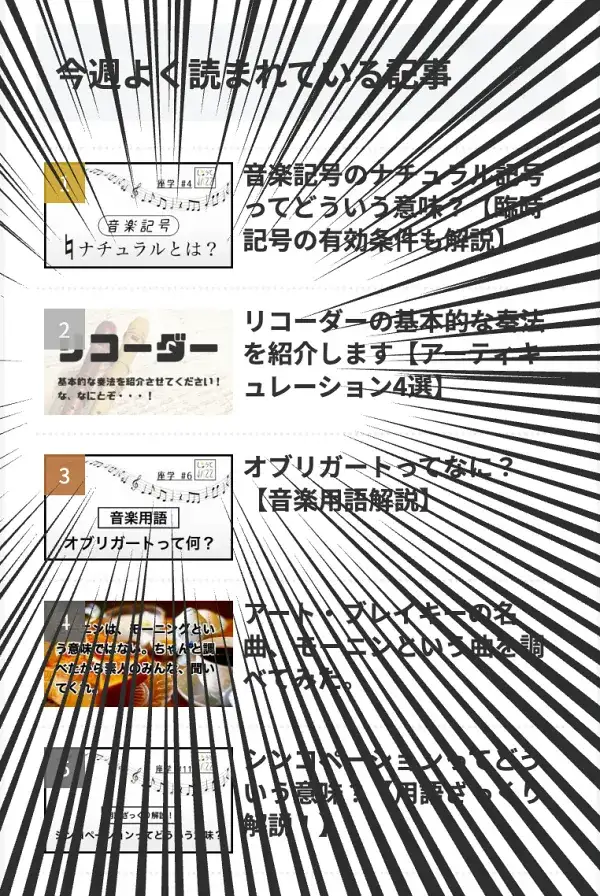
![]() わあ、ほんまや。
わあ、ほんまや。
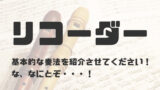
リコーダーとは?
![]() そもそもリコーダーとは?というところから話をさせてください!
そもそもリコーダーとは?というところから話をさせてください!
![]() リコーダーとは、ヨーロッパ発祥の木管楽器で縦笛の一種である。
リコーダーとは、ヨーロッパ発祥の木管楽器で縦笛の一種である。
![]() やっぱり学校教育で使われる楽器のイメージが強いですね。ピアニカと双璧を成す初等教育における代表楽器。
やっぱり学校教育で使われる楽器のイメージが強いですね。ピアニカと双璧を成す初等教育における代表楽器。
![]() その点でリコーダーが選ばれたのは、シンプルな構造なのが大きいのではないかな?リコーダーは息を吹き込むだけで音が出るので、演奏のハードルがとても低い。また、リードを持たないため、アイテム点数が少なく、クラリネットやサックスのような楽器よりもメンテナンスが圧倒的に楽なんじゃな。大きさも小さいし軽いので、生徒全員が持つにはちょうど良い楽器だったんじゃないかな。
その点でリコーダーが選ばれたのは、シンプルな構造なのが大きいのではないかな?リコーダーは息を吹き込むだけで音が出るので、演奏のハードルがとても低い。また、リードを持たないため、アイテム点数が少なく、クラリネットやサックスのような楽器よりもメンテナンスが圧倒的に楽なんじゃな。大きさも小さいし軽いので、生徒全員が持つにはちょうど良い楽器だったんじゃないかな。

リコーダーの歴史
![]() そもそもリコーダーっていつからあるんですか?
そもそもリコーダーっていつからあるんですか?
![]() 中世ヨーロッパの13世紀頃にはすでに存在していたとされておる。ルネサンス期には宮廷音楽や宗教音楽の演奏に使用され、この時にさまざまなサイズのリコーダーが作られたのじゃ。
中世ヨーロッパの13世紀頃にはすでに存在していたとされておる。ルネサンス期には宮廷音楽や宗教音楽の演奏に使用され、この時にさまざまなサイズのリコーダーが作られたのじゃ。
![]() 縦笛自体は紀元前からあるし、もっと大昔に作られたと思っていたんですけど、リコーダーの形が確立されたのは意外と最近なんですね!
縦笛自体は紀元前からあるし、もっと大昔に作られたと思っていたんですけど、リコーダーの形が確立されたのは意外と最近なんですね!
![]() 確かにそうじゃな。そこからリコーダーはさらに洗練されていって、バロック時代には、ヴィヴァルディやバッハなどの作曲家がリコーダーのための作品を残していたりするぞ。ただ、18世紀後半になるとフルートなどの楽器が発展し、リコーダーは次第に表舞台から姿を消すことになるという・・・。
確かにそうじゃな。そこからリコーダーはさらに洗練されていって、バロック時代には、ヴィヴァルディやバッハなどの作曲家がリコーダーのための作品を残していたりするぞ。ただ、18世紀後半になるとフルートなどの楽器が発展し、リコーダーは次第に表舞台から姿を消すことになるという・・・。
![]() うーん、音の響きを考えるとクラシックの世界でフルートには勝てんか・・・。
うーん、音の響きを考えるとクラシックの世界でフルートには勝てんか・・・。
![]() しかしじゃ、20世紀に入ると、古楽復興の流れの中でリコーダーの価値が再評価され、教育現場やアマチュア音楽家の間で広く親しまれるようになったのじゃ。そして、今でも誰もが触れたことのある身近な楽器として愛されておるのよお。
しかしじゃ、20世紀に入ると、古楽復興の流れの中でリコーダーの価値が再評価され、教育現場やアマチュア音楽家の間で広く親しまれるようになったのじゃ。そして、今でも誰もが触れたことのある身近な楽器として愛されておるのよお。
![]() おお、一度は消えかけたリコーダーが再び使われるようになったんですね!そういう経緯で僕たちとリコーダーは出会えているんですね!
おお、一度は消えかけたリコーダーが再び使われるようになったんですね!そういう経緯で僕たちとリコーダーは出会えているんですね!

リコーダーの種類
![]() リコーダーにはたくさんの種類があるんですよ。種類によって音域が異なるので、リコーダーだけでアンサンブルを奏でることも多いんですよね。
リコーダーにはたくさんの種類があるんですよ。種類によって音域が異なるので、リコーダーだけでアンサンブルを奏でることも多いんですよね。

![]() テレマン楽器のリコーダー販売サイトさんのリコーダーの種類が分かりやすかったので拝借して引用させていただきました!この場を借りてお礼申し上げます!
テレマン楽器のリコーダー販売サイトさんのリコーダーの種類が分かりやすかったので拝借して引用させていただきました!この場を借りてお礼申し上げます!
クライネソプラニーノ・リコーダー
クライネソプラニーノ・リコーダーは、最も高音域を持つ小型のリコーダーです。その高音域のため、演奏には高度な技術が求められますが、独特のクリアな響きを持っています。
ソプラニーノ・リコーダー
ソプラニーノ・リコーダーは、ソプラノ・リコーダーよりもさらに高い音域を持つ小型のリコーダーです。明るく華やかな音色が特徴です。
ソプラノ・リコーダー
ソプラノ・リコーダーは、学校教育で最も一般的に使われるリコーダーです。明るく澄んだ音色が特徴で、音域は中高音域に位置します。比較的コンパクトなサイズのため、初心者でも扱いやすい楽器です。
また、ソプラノ・リコーダーにはジャーマン式とバロック式という2つの運指体系が存在します。ジャーマン式は初心者向けに設計されており、指使いがシンプルですが、音の正確さに制限があるため、上級者にはバロック式が推奨されます。バロック式はより本格的な音楽演奏に適した運指体系を持ち、プロの演奏家もこちらを使用することが多いです。
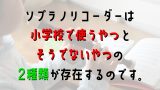
アルト・リコーダー
アルト・リコーダーは、ソプラノ・リコーダーよりもサイズが大きく、低い音域を持っています。音色は深みがあり、豊かな響きを持っています。バロック音楽などでは主旋律を奏でることも多く、リコーダー・アンサンブルにおいて重要な役割を果たします。
テナー・リコーダー
テナー・リコーダーは、アルト・リコーダーよりさらにサイズが大きく、低音域を担当します。音色は柔らかく暖かみがあり、演奏するときにはやや広げた指使いが求められます。そのため、小さな手の人にはやや扱いづらいかもしれません。
バス・リコーダー
バス・リコーダーは、さらに低音域を担当し、重厚な響きを持つ楽器です。サイズが大きいため、キー(レバー)が装備されており、指を大きく広げなくても演奏しやすくなっています。リコーダー・アンサンブルでは低音部を支える役割を果たします。
大バスリコーダー
大バス・リコーダーは、バス・リコーダーよりもさらに低い音域を担当する大型のリコーダーです。全長がかなり長いため、演奏者は座って演奏することが一般的です。音色は深く豊かで、アンサンブルでは重要な低音パートを担います。
コントラバス・リコーダー
コントラバス・リコーダーは、リコーダーの中でも最も低い音域を持つ楽器です。大バス・リコーダーよりもさらに大型で、管の形状が折り曲げられていることが多く、演奏時には専用のスタンドを使用することもあります。豊かで深みのある低音が特徴で、リコーダー・アンサンブルの低音部を支える重要な楽器です。
リコーダーのジャズ
![]() リコーダーを使ったジャズを聴けたりするんですか?
リコーダーを使ったジャズを聴けたりするんですか?
![]() マルチ・リード奏者が実験的にたまにリコーダーを楽曲に入れることもあるが、今回は、リコーダー・アンサンブルを行うグループ、フルート・アロー!(Flute Alors!)を紹介しよう。モントリオールを拠点として、プロ・リコーダー・アンサンブルとして演奏活動を行っているグループなんじゃよ。
マルチ・リード奏者が実験的にたまにリコーダーを楽曲に入れることもあるが、今回は、リコーダー・アンサンブルを行うグループ、フルート・アロー!(Flute Alors!)を紹介しよう。モントリオールを拠点として、プロ・リコーダー・アンサンブルとして演奏活動を行っているグループなんじゃよ。
![]() へ〜!初めて知りました!
へ〜!初めて知りました!
![]() そのフルート・アロー!のアルバム『Bach’N’Jazz』では、バッハとジャズのスタンダード・ナンバーをリコーダー・カルテット用にアレンジしておるぞ。フランク・シナトラで有名な「フライ・ミー・トゥー・ザ・ムーン」、ジョセフ・コズマ作曲の「枯葉(Les feuilles mortes)」、トランペット奏者ディジー・ガレスピーの代表曲「チュニジアの夜」など、ジャズ・スタンダードの名曲が収録されているのでぜひ聴いてみて欲しい。
そのフルート・アロー!のアルバム『Bach’N’Jazz』では、バッハとジャズのスタンダード・ナンバーをリコーダー・カルテット用にアレンジしておるぞ。フランク・シナトラで有名な「フライ・ミー・トゥー・ザ・ムーン」、ジョセフ・コズマ作曲の「枯葉(Les feuilles mortes)」、トランペット奏者ディジー・ガレスピーの代表曲「チュニジアの夜」など、ジャズ・スタンダードの名曲が収録されているのでぜひ聴いてみて欲しい。
![]() 僕の好きなスタンダードだ!『チュニジアの夜』とかどんな感じになるんだろう。聴くのが楽しみです!
僕の好きなスタンダードだ!『チュニジアの夜』とかどんな感じになるんだろう。聴くのが楽しみです!
おわりに
![]() いかがだったかな?リコーダーは、シンプルながらも奥深い楽器であり、初心者から上級者まで楽しめる楽器なのじゃ。ソロ演奏からアンサンブルまで、さまざまな場面で活躍するリコーダーの魅力を、ぜひ改めて体験してみてもらえると嬉しいのう。
いかがだったかな?リコーダーは、シンプルながらも奥深い楽器であり、初心者から上級者まで楽しめる楽器なのじゃ。ソロ演奏からアンサンブルまで、さまざまな場面で活躍するリコーダーの魅力を、ぜひ改めて体験してみてもらえると嬉しいのう。
![]() 大人になってからソプラノ・リコーダーとアルト・リコーダーを買ってみたんですけど、めっちゃ楽しいですよ!
大人になってからソプラノ・リコーダーとアルト・リコーダーを買ってみたんですけど、めっちゃ楽しいですよ!
4コマ作者
![]() 502
502
商業誌での受賞経験あり。
約1年間Web連載の漫画原作(ネーム担当)経験あり。
2019年よりフリーで活動中。
Xはこちら