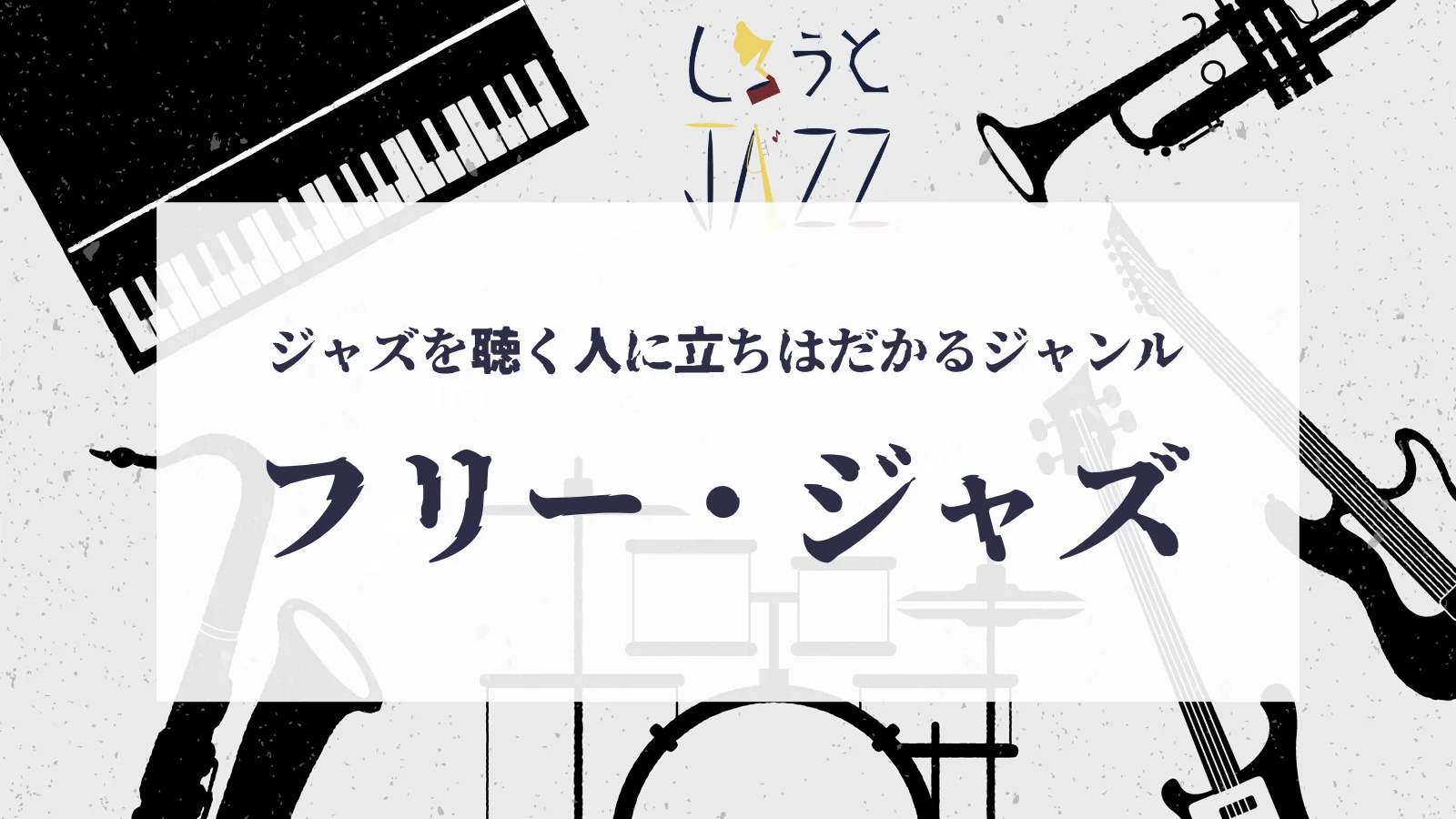どうも、ズワイガニです。
ジャズを聴いていくと、あるところで必ず立ちはだかるジャンルがあります。
それが「フリー・ジャズ」。
ビバップ、ハード・バップ、モード・ジャズなどを経て、ジャズの演奏スタイルにある程度慣れてきた時に、このフリー・ジャズに出会うとこう思うことが多いのではないでしょうか。
「これはジャズなのか?」
「どう聴けばいいのかわからない」
「ただの騒音にしか聴こえない」
しかし、このわからなさこそがフリー・ジャズの魅力であり、ジャズの歴史における大きな意味でもあるのです。
今回は、そんなフリー・ジャズの基本的な考え方や歴史的背景、聴き方のヒント、さらに実際に聴くべき名盤を紹介していきます。
フリー・ジャズとは?
フリー・ジャズは、その名の通り「自由なジャズ」を意味します。
1950年代後半から1960年代にかけて登場したスタイルで、それまでのジャズを支配していたコード進行や決まった形式から解放され、より自由な表現を追求したものです。
従来のジャズでは、
- テーマ(曲のメロディ)
- ソロ(和声の枠組みであるコード進行の上での即興)
- 再びテーマに戻る
という流れが基本でした。つまり、自由な即興と言いつつも、実際にはしっかりとしたルールの上で展開されていたのです。
一方でフリー・ジャズは、そのルール自体を壊そうとした音楽です。テーマすらない場合もあり、複数の演奏者が同時に即興を繰り広げることで、混沌としたサウンドが生まれます。
例えば、フリー・ジャズを初めて聴く人は「全員が好き勝手に演奏しているだけ」と思うかもしれません。確かに耳慣れたメロディやリズムが少なく、調性も崩れるため、その印象は自然です。
ですが、その背後には「従来の形式に縛られない、新しい音楽表現への挑戦」という強い意志があります。
フリー・ジャズの起源
フリー・ジャズの誕生は、1950年代後半から1960年代初頭にかけてのアメリカが舞台です。この時代は、公民権運動の高まりや社会の変化と深く結びついており、ジャズもまた自由を求める大きなうねりに巻き込まれていました。
オーネット・コールマンの登場
フリー・ジャズを語る上で欠かせない人物がオーネット・コールマン です。1959年に発表したアルバム『The Shape of Jazz to Come』は、そのタイトル通り「これからのジャズのかたち」を示すものでした。従来のコード進行に縛られず、旋律とリズムの自由なやり取りを中心に展開される演奏は、当時のジャズ界に衝撃を与えます。
さらに1960年にはアルバム『Free Jazz』をリリース。これは左右に分かれた2つのクインテットが同時に即興を繰り広げるという実験的な作品で、「フリー・ジャズ」というジャンル名を決定づけた歴史的アルバムです。
ジョン・コルトレーンの進化
もうひとり重要なのが ジョン・コルトレーン。彼はモード・ジャズの発展を経て、次第に自由度を増した演奏へと傾倒していきました。代表作『Ascension』(1965年)は、大編成のアンサンブルによるフリー・ジャズ的な試みであり、従来のファンを驚かせると同時に、新たな表現の可能性を切り開きました。
その他の重要な潮流
- セシル・テイラー(ピアノ):リズムと和声の概念を徹底的に破壊し、打楽器的アプローチで新境地を切り開いた。
- アルバート・アイラー(サックス):ゴスペルやマーチの要素を取り込み、祈りのような熱量を持った演奏を展開。
こうした動きは、単なる音楽上の実験にとどまらず、当時の黒人社会における「解放」の意識とも強く結びついていました。フリー・ジャズは、時代の精神を体現した表現手段でもあったのかもしれません。
フリー・ジャズにもルールはあるの?
「フリー・ジャズ=無秩序」と思われがちですが、実際にはそうではありません。確かにコード進行や形式といった従来の枠組みは外れていますが、代わりに新しい論理や約束事が存在します。ここを理解すると、フリー・ジャズは単なる混沌ではなく新しい秩序の探求であることが見えてきます。
コード進行からの解放
従来のジャズでは「循環コード(II-V-I進行など)」が演奏の基盤でした。しかし、フリー・ジャズではこの縛りを外すことで、演奏者は任意の音を選び、瞬間的にフレーズを構築できるようになります。
つまり「コード進行のルールを使わない」=「別のルールに基づく」ということです。
ハーモロディクスという理論
別のルールに基づくということの代表例が、オーネット・コールマンの独自の理論、ハーモロディクス(Harmolodics)です。
ハーモロディクスの要点は以下の通りです。
- すべての音は平等:特定のコード・キーに縛られず、どの音も同じ価値を持つ。
- 旋律・リズム・ハーモニーの同等性:従来は和音(ハーモニー)が旋律を規定していたが、ハーモロディクスでは旋律も和音もリズムも対等。
- 演奏者間の相互作用:音の選択は自由だが、他者の音に即座に反応することで音楽が成立する。
つまり、フリー・ジャズの「自由」は、完全な無秩序ではなく、「すべてを同等に扱う」という論理に基づいた秩序だといえます。
演奏の会話性というルール
フリー・ジャズでは、テーマやコードに従う代わりに、演奏者同士が即興的な会話をすることが最大のルールです。
ある奏者が放ったフレーズに対して、別の奏者が反応し、さらに別の楽器がそれに加わる――そのやり取りの連鎖が音楽を形づくります。
この点では、むしろ通常のジャズ以上に高度なリスニング能力と瞬発力が要求されると言えるでしょう。
フリー・ジャズを聴くために覚えておくこと
フリー・ジャズに初めて触れたとき、多くの人が「何を聴けばいいのかわからない」と感じます。これは当然のことで、従来のジャズにあったメロディやコード進行といったわかりやすい道しるべが、フリー・ジャズにはほとんど存在しないからです。
では、どうすればフリー・ジャズを楽しめるようになるのでしょうか?
ここでは、聴き方のヒントをいくつか紹介します。
演奏者同士の会話を意識する
フリー・ジャズは、個々の演奏者が勝手に音を出しているのではなく、即興的な対話で成り立っています。
ある楽器がフレーズを投げかければ、別の楽器が応答する。時には同意し、時には反発し、そこからまた新しい音楽が展開していきます。
聴くときは、誰が誰に呼びかけているのかに注目すると、混沌に見えた音楽が会話劇のように浮かび上がってきます。
音のエネルギーを感じる
フリー・ジャズはメロディやハーモニーを超えて、純粋な音のエネルギーや質感を楽しむ音楽でもあります。
金管楽器のブロー、サックスの叫び、ピアノの打鍵、ドラムの連打――それらを音楽的に整ったフレーズとしてではなく、生のエネルギーとして受け止めてみましょう。
「理解する」のではなく「浴びる」。といえば分かりやすいかもしれません。
短い演奏から入ってみる
フリー・ジャズのアルバムは、20分以上に及ぶ長尺の演奏も珍しくありません。
最初からそうした大作に挑むと疲れてしまうので、まずは5分前後の短めの曲から慣れていくのがおすすめです。
例えばオーネット・コールマンの初期作品には、比較的コンパクトで聴きやすいトラックも多く、フリー・ジャズ入門には向いています。
従来のジャズを踏まえて聴く
フリー・ジャズは、それまでのジャズの延長線上に生まれたものです。ビバップやハード・バップ、モード・ジャズをある程度聴いてからフリーに触れると、何を壊そうとしたのかが理解でき、受け入れやすくなります。
逆に言えば、いきなりフリー・ジャズから入ると「これは音楽なのか?」と混乱してしまうので、ある程度モダン・ジャズを理解してから聴いてみることをオススメします。
実際に聞いてみよう!フリー・ジャズの必聴アルバム3選
フリー・ジャズを理解するには、実際に作品を聴いてみることが一番の近道です。
ここでは、入門者にもおすすめできる代表的な3枚を紹介します。
1. Free Jazz / オーネット・コールマン (1960)
![]() フリー・ジャズというジャンル名を決定づけた歴史的アルバム。左右のチャンネルに別々のクインテットを配置し、合計8人が同時に即興を繰り広げるという前代未聞の試みである。一聴すると混沌としているが、注意深く聴くと、奏者同士が呼応し合う瞬間が随所に現れる自由即興の原点を知るには欠かせない一枚なのだ。
フリー・ジャズというジャンル名を決定づけた歴史的アルバム。左右のチャンネルに別々のクインテットを配置し、合計8人が同時に即興を繰り広げるという前代未聞の試みである。一聴すると混沌としているが、注意深く聴くと、奏者同士が呼応し合う瞬間が随所に現れる自由即興の原点を知るには欠かせない一枚なのだ。
2. Ascension / ジョン・コルトレーン (1965)
![]() モード・ジャズの探求を経て、コルトレーンが到達したフリー・ジャズ期の代表作。11人編成の大バンドによる集団即興は、祈りや叫びのような圧倒的エネルギーを放っている。途中でソロと全員演奏が交互に現れる構成なので、無秩序ではなく明確な流れがあることも感じられ、フリー・ジャズの精神性を体感できる名盤である。
モード・ジャズの探求を経て、コルトレーンが到達したフリー・ジャズ期の代表作。11人編成の大バンドによる集団即興は、祈りや叫びのような圧倒的エネルギーを放っている。途中でソロと全員演奏が交互に現れる構成なので、無秩序ではなく明確な流れがあることも感じられ、フリー・ジャズの精神性を体感できる名盤である。
3. Unit Structures / セシル・テイラー (1966)
![]() ピアニスト、セシル・テイラーによる代表作。ピアノを打楽器のように扱うスタイルで、従来の和声やリズムを徹底的に解体した演奏が展開される。難解と思われがちだが、アンサンブル全体を「音の建築物」として聴くと、そのタイトル通りの壮大さが伝わってくるぞ。フリー・ジャズの理論性と実験精神を感じられる作品である。
ピアニスト、セシル・テイラーによる代表作。ピアノを打楽器のように扱うスタイルで、従来の和声やリズムを徹底的に解体した演奏が展開される。難解と思われがちだが、アンサンブル全体を「音の建築物」として聴くと、そのタイトル通りの壮大さが伝わってくるぞ。フリー・ジャズの理論性と実験精神を感じられる作品である。
おわりに
フリー・ジャズは、ジャズを聴く人にとって避けては通れないジャンルです。初めて耳にしたときは「何が起こっているのか全然わからない」と感じるかもしれません。しかし、それはフリー・ジャズが意図的に従来の枠組みを外し、自由を追求した音楽だからこそ。
大切なのは、「Don’t Think. Feel!」です。
![]() ブルー・スリー?
ブルー・スリー?
メロディやコードを追う代わりに、演奏者同士の会話、音のぶつかり合いや共鳴、エネルギーの流れが重要なんです。
フリー・ジャズは無秩序に見えて、その実、非常に高度なコミュニケーションの上に成り立っています。最初は難しくても、繰り返し聴くうちに、混沌の中から秩序や美しさが立ち現れる瞬間が訪れるはずです。(ね、ジャズってハードル高いよね(笑))
この分かるようになるまでの体験も含めてジャズが楽しいところなんですよね〜!って言っている私はまだまだ全然フリー・ジャズのことは分かっていないんですけどね(笑)