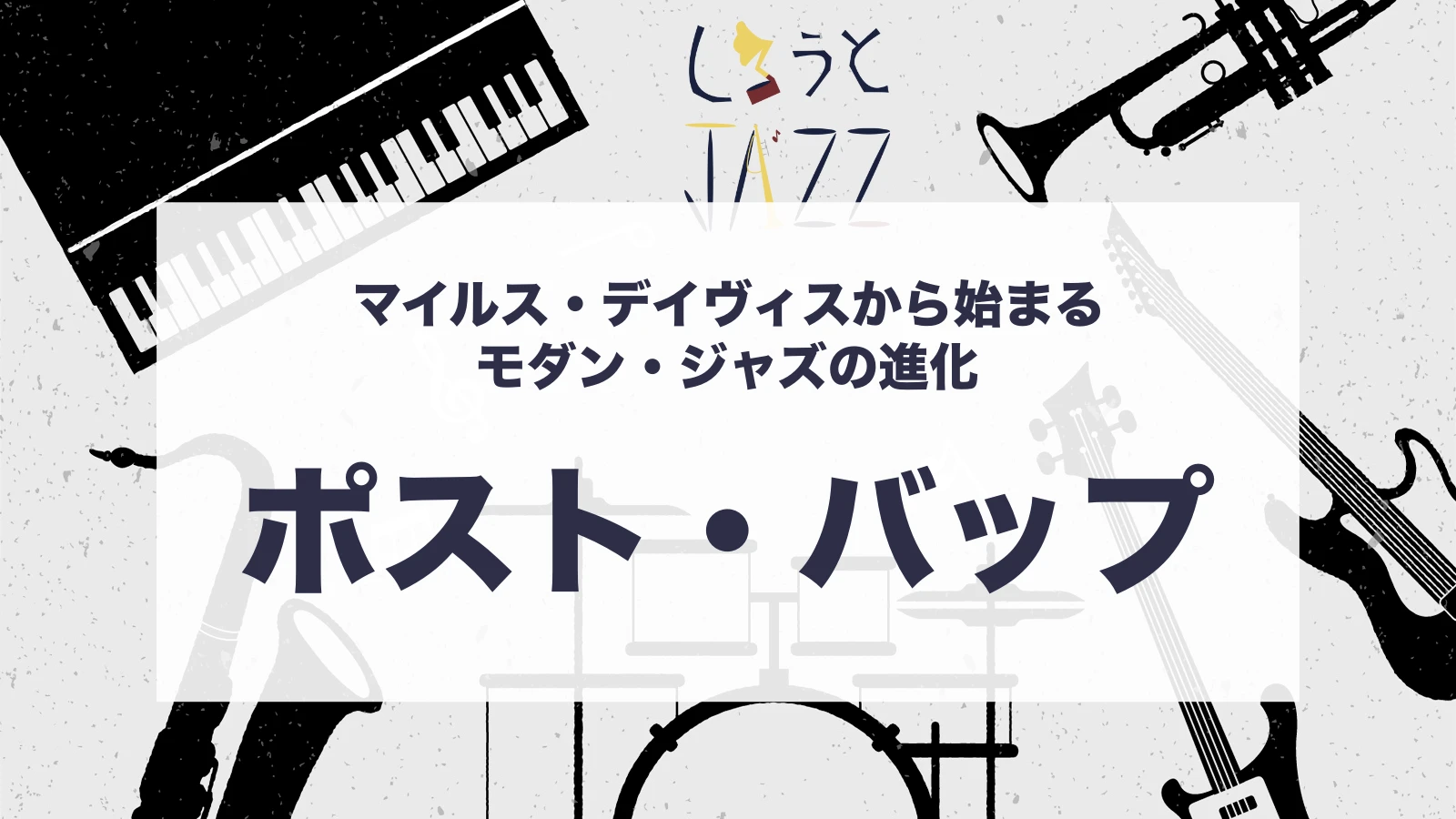どうも、ズワイガニです。
ジャズの中でもポスト・バップという言葉を聞くと、なんだか難しそうに感じるかもしれません。
けれど実はこのスタイル、自由さと知性のバランスが絶妙で、深く聴くほどハマるタイプの音楽なんです。
1950年代の終わりから60年代にかけて、マイルス・デイヴィスやジョン・コルトレーンをはじめとする名手たちが、ビバップやモード・ジャズの先に新しい表現を模索しました。
その結果生まれたのが、ポスト・バップです。
今回は、ポスト・バップを初心者にもわかりやすく、時代背景から代表作、そして聴き方のヒントまで紹介していきます!
ポスト・バップとは?
1950年代の終わり、ジャズは大きな転換点を迎えていました。
当時主流だったビバップは、スピード感と高度な即興性でジャズを芸術の領域へと押し上げましたが、一方で「もっと自由に、もっと深く音を探りたい」と考えるミュージシャンたちが現れます。
そんな流れの中で、1959年にマイルス・デイヴィスが発表した名盤『Kind of Blue』がモード・ジャズという新たな表現の可能性を示しました。
そして1960年代に入ると、ハード・バップやモード・ジャズ、さらにはフリー・ジャズの要素をも融合させたスタイルが生まれます。
それが、後にポスト・バップと呼ばれる潮流です。
“ポスト”とは「〜の後」という意味。つまりビバップのあとに生まれた音楽、という位置づけではありますが、実際にはひとつのスタイルを超えて、新しい可能性を追い求めた音楽と言えるでしょう。
この時期の象徴的な存在が、マイルス・デイヴィスの第二期クインテット(1964〜68)です。
メンバーは、ウェイン・ショーター(サックス)、ハービー・ハンコック(ピアノ)、ロン・カーター(ベース)、トニー・ウィリアムス(ドラム)という錚々たる顔ぶれでした。
彼らはステージ上で、常に即興で構成を変え、まるで会話をするように音でぶつかり合いながらも、一体感のある生きた音楽を作り上げていきます。
その姿勢こそ、ポスト・バップの核心だと思います。
ビバップの緊張感、モードの余白、そして新しいハーモニーの探求。それらを融合したポスト・バップは、知的でありながら情熱的な魅力を持ったスタイルなんです。
代表的なアーティストと名盤
前述したように、ポスト・バップを語る上で中心となるのが、マイルス・デイヴィスの第二期クインテット(1964〜68)です。このバンドが残した作品群は、ポスト・バップの方向性を決定づけたといっても過言ではありません。
まず聴いておきたいのが、アルバム『E.S.P.』(1965)。
従来のジャズの枠を超え、演奏の中で即興的に構成を変化させていく会話のような演奏が、ポスト・バップの真髄です。ひとつのフレーズに他のメンバーが瞬時に反応し、音楽がその場で姿を変えていく。まさにライヴで進化する音楽と呼ぶにふさわしい一枚です。
続いておすすめしたいのが、ピアニストのハービー・ハンコックによる『Maiden Voyage』(1965)。
穏やかな海の旅をテーマにしたアルバムで、美しいメロディの中に静かな緊張感が漂います。リリカルでありながら知的、まさにポスト・バップの魅力が凝縮された作品です。
また、サックス奏者、ウェイン・ショーターの『Speak No Evil』(1966)も外せません。
幻想的でミステリアスなハーモニーが印象的で、彼独自の詩的なジャズの世界を切り開いた名盤です。
さらに、ピアニストであるマッコイ・タイナーの『The Real McCoy』(1967)や、トランペッターであるフレディ・ハバードの『Hub-Tones』(1962)も聴き応え十分。それぞれが異なる個性を持ちながらも、共通して感じられるのはジャズを次の段階へ押し進めようというエネルギーです。
どのアルバムも、最初は少し難しく感じるかもしれませんが、何度か聴くうちに、音の中に意志や会話が見えてきます。それこそが、ポスト・バップが今も多くのファンに愛される理由なのです。
初心者におすすめの聴き方
ポスト・バップは、理屈より流れで楽しむのがコツです。
まずは、1曲を最初から最後まで会話を聞くように聴いてみてください。
ピアノとサックスが掛け合う。ドラムが一瞬で空気を変える。ベースが全体を支えながらも、時に主張する。
それぞれが自分の意見を持ちながらも、全体で調和している、まるでジャズ・クラブのステージで、5人が真剣に議論しているような感覚です。
もし構成が難しく感じたら、音のやり取りに注目してみましょう。
サックスがフレーズを吹けば、ピアノがすぐに反応する。ドラムがリズムを変化させると、ベースが新しいラインを描く。そんな音と音のキャッチボールを感じ取るだけでも、演奏が一気に立体的に聴こえてきます。
「あ、この瞬間いいな」と思った場所があれば、それだけで十分!その一瞬を味わうことこそ、ポスト・バップの楽しみ方だと思います!
おわりに
いかがでしたか?
少しとっつきにくそうに思えるポスト・バップですが、聴けば聴くほど面白くなるタイプの音楽ですので、気負わずに、まずは一曲聴いてみてくださいね!