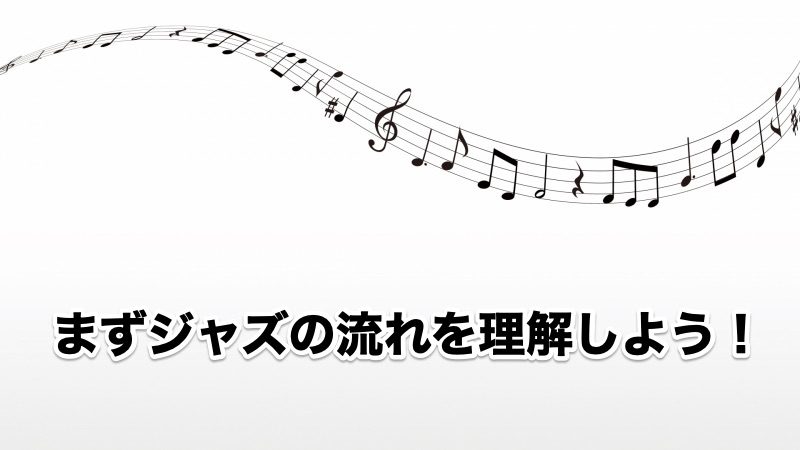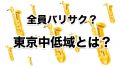どうも、ズワイガニです。
素人にはジャズを簡単に説明されても分からないということがあります。僕がそうだからそういうことがあるってことにしておきます。
『4拍子の偶数拍を強くすると…』とか言われても理屈ではわかるが、実際に曲を聴いてみるとまったくピンとこないので、結局どういうことだってばよ!ってなります。
なので、素人にも分かるような視点でジャズの理解を深めたいと思います。
ジャズの要素
オーソドックスなジャズを聴いてざっくり分解すると、曲の流れは3つに分けられていると考えます。
- イントロ
- テーマ(メロディ)
- アドリブ(インプロヴィゼーション)
この3つの要素です。この要素を理解すると、曲の流れが分かるので、ジャズの聴き方が少し分かるようになると思います。
次に、この3つの要素を説明するのでこのまま聞いてくださいな。
イントロ
まず、イントロですが、これはテーマを盛り上げるためにある前説的な役割ですね。
ボキャブラリーがないので、こんな例えになってしまうんですけど…。
若手漫才師を決めるコンテスト『M-1グランプリ』でいうと、漫才師の紹介動画が差し込まれてから「レディゴーゴーゴー…!」みたいな出囃子が鳴って漫才が始めるまでをイントロだと思ってください。
すごく例えがわかりづらいし、イントロぐらいわかるし、例えがわかりづらいと思いつつも、この例えによってあることに気が付かないでしょうか?
そう、イントロはあってもなくても良い。ということです。別にイントロから始めても良いし、いきなりテーマに入っても良い。自由。
イントロを無視しても良いけど、曲の一部としてすでにイントロが入っている曲があります。そういう既に曲に組み込まれているイントロを『ヴァース』と呼ぶそうです。
また、元々イントロが付いていなかったけど、(作曲者ではない人の)後付けのイントロが良い感じだったので、それが定番化するみたいな事例がジャズにはたくさんあります。
テーマ
テーマ、主題ですね。
楽曲構成の中で、主旋律(メロディ)が提示される部分を指します。楽曲全体の骨組みとなる部分です。このテーマが演奏の基盤となり、その後に続くアドリブでさまざまに展開されます。
たとえば、ジャズの一般的な形式である「ヘッド・ソロ・ヘッド」の構成では、最初にテーマ(ヘッド)が演奏され、そのあとにソロ演奏が続き、最後に再びテーマが演奏されて締めくくられます。このようにテーマは楽曲全体をつなぎ、聴衆に楽曲の基調を伝える重要な役割を果たしています。
アドリブ
さいごにジャズの醍醐味、アドリブです。
だいたいの曲はテーマが終わったあとにアドリブ演奏が始まります。ラップバトルみたいにそれぞれのプレイヤーが交代で即興演奏していくのが一般的です。プレイヤーが満足したら次のプレイヤーにバトン・タッチするのが通常運転なのだそう。
その間、ドラムやベースといったリズム隊は自分のソロでない時も演奏を支えていることが多いです。盛り上がりに合わせて決め打ちなどを行い、ソロ・プレーヤーの即興演奏に合わせていたりするので、リズム隊はとってもクールな役割なんです。
で、このアドリブ・パート。決して適当に好き放題吹いているわけではないのです。
ここでテーマの重要性が出てきます。
アドリブ・パートはテーマのメロディ・コードに付随したものであるので、曲のコード進行に沿って演奏する必要があります。
どういうことかと言うと、メロディ・コードの中の使える音はだいたい決まっているので、その使える音の範囲で即興演奏しましょうね。ってことなんです。
そういうわけで、アドリブ・パートが終わったら、再度テーマに戻って曲が終わるとなんか収まりが良い感じがするんですね。
ちなみに、この記事で私は即興部分をアドリブと呼んでいますが、ソロ・パートにおける即興演奏をインプロヴィゼーションと呼ぶことが一般的のように思います。
この辺は人によって微妙に定義が違うので、このブログではそういうことにしておきます。
アドリブ・パートはアドリブなのか
ところで、よく分からない見出しになりましたが、やはり素人からするとアドリブ演奏は「本当かよ〜!!?」って思っちゃいますよね。
だって「曲何が良い?」「これでいこう」なんてやりとりで選曲してから、曲に応じた即興演奏するなんてすごすぎでしょ。
でも、これは本当なのです。即興演奏はリアルタイムで作曲していることになるんですけど、おそらく真っ白な状態から作っているわけではなく、フレーズやフレーズを繋ぐブリッジ部分といった自分の引き出しにある音をその場で取り出してアレンジしていたりするのだと思います。
また、たとえ詰まって空白が生まれても音楽的に破綻していなければOKなのだそう。こういうライヴ感がジャズの魅力なのだろうな、と思う。
実際に聴いてみよう
ここまででジャズの流れがなんとなくわかったかな?実際に聴いてみるとかなり分かりやすいぞ☆
そこで、選曲した曲がこれです!
『November Afternoon(ノヴェンバー・アフターヌーン)』
ディジー・ガレスピー
ディジー・ガレスピーさんの演奏です。
曲がったトランペットを持った変わったおっちゃんです。

この記事は、クリエイティブ・コモンズ・表示・継承ライセンス3.0のもとで公表されたウィキペディアの項目「ディジー・ガレスピー」を素材として二次利用しています。
代表曲に『チュニジアの夜』などがあり、モダン・ジャズの礎を築いたすごい人です。
ちなみに、この曲がったトランペットは最初事故によって曲げられたものだったが、これを気に入った以後は特注で作ってもらっていたらしい。
さて、この曲は、イントロ→テーマ→アドリブ→テーマ で完結していて、非常に聴きやすかったので、選びました。聴いてみて、「あ〜なるほどね」って思っていただけたら、この記事で言いたかったことは伝わっていると思います。実際に聴いて流れを理解してみてくださいね!
さいごに
ここまでお読みいただきありがとうございました。
覚えた知識をすぐさま記事にしているズワイガニです。間違っていたりしたら、訂正しますので、教えていただけると助かります。
ということで、初心者仲間のみなさま、今後ともよろしくお願いします。
それでは、ズワイガニでした!