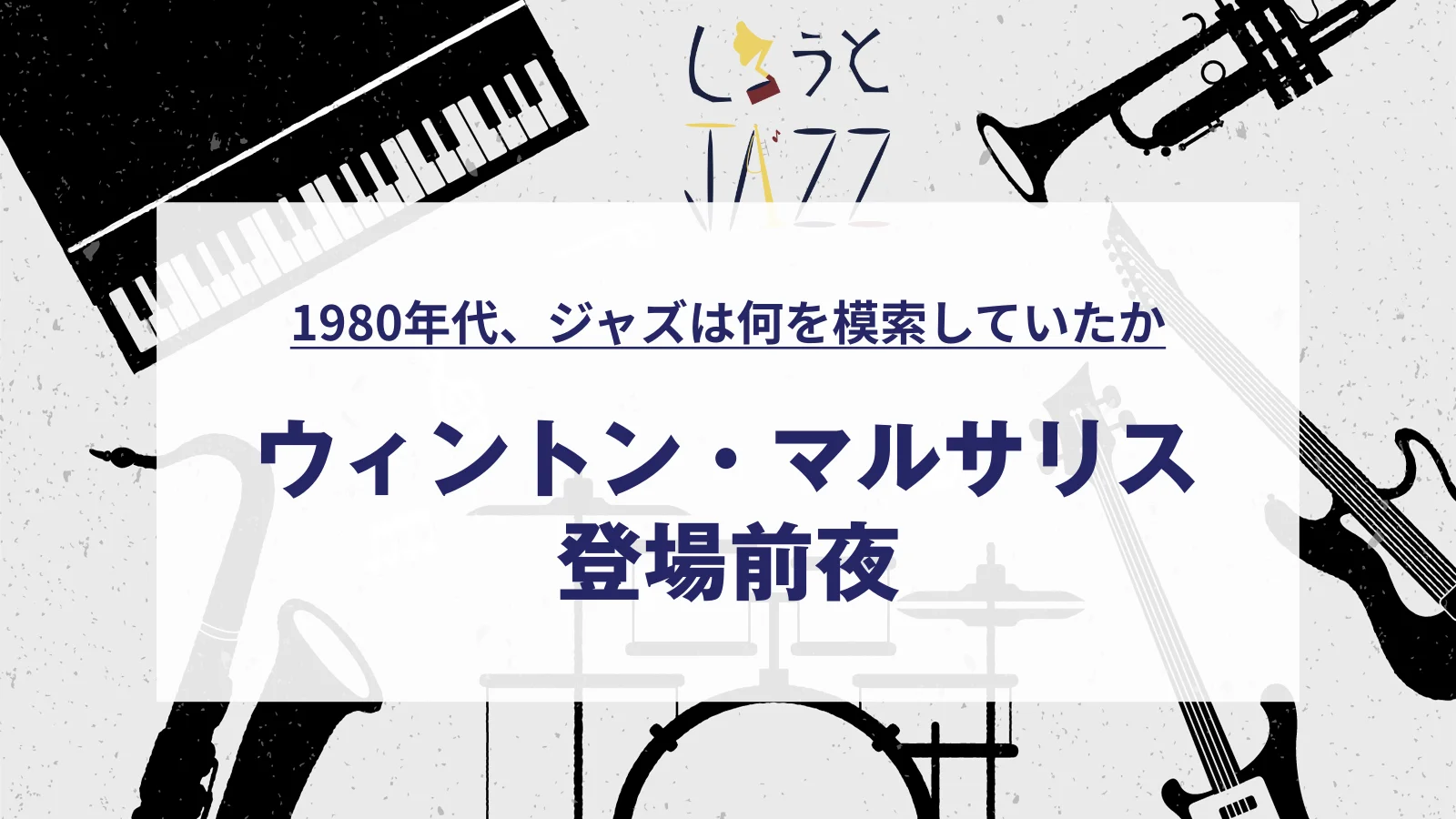どうも、ズワイガニです。
1980年代のジャズは、「保守」と「革新」、「商業」と「芸術」のはざまで揺れ動いていました。
1970年代に隆盛を極めたフュージョンやクロスオーヴァー。その余波が続くなかで、「次のジャズはどこへ進むのか?」という問いが、プレイヤーやリスナーのあいだでくすぶり続けていたのです。
そして1982年、ウィントン・マルサリスがメジャー・デビューを果たし、シーンは大きな転換点を迎えます。その登場以前、1980年代初頭の現場ではどのような模索が続いていたのでしょうか?
今回は、この過渡期にあったジャズの風景を振り返ってみたいと思います。
クロスオーヴァー全盛のその先へ
1970年代、マイルス・デイヴィスが開いた電化の扉は、ウェザー・リポートやリターン・トゥ・フォーエヴァー、ハービー・ハンコックの『Head Hunters』といったフュージョン勢によって受け継がれ、ジャズはファンクやロックと結びつきながら大胆に拡張されていきました。
この流れは商業的にも大きな成功を収めましたが、その一方で「ジャズ本来の精神性が失われてしまったのではないか」という懐疑の声も上がります。
サウンド重視の方向性が即興性やインタープレイの緊張感を薄め、「ジャズの核心」が曖昧になったと考える人も少なくありませんでした。
模索する若手たち 〜ブランフォードとメセニーの存在〜
1980年代に入ると、フュージョンの進化が行き着く先を見つめながら、「ここからどこへ行くべきか?」を考える若手ミュージシャンたちが台頭してきます。
サックス奏者ブランフォード・マルサリスは、その代表格と言えるでしょう。クラシックからポップスまで幅広いジャンルをこなせる柔軟さを持ちながら、ジョン・コルトレーン譲りのストイックな即興演奏や音楽観を大切にしていました。
後にスティングのバンドに参加するなどポップスの世界にも進出しますが、その芯には常にジャズへの深い敬意があったのです。彼の姿勢は、80年代のジャズが抱えていた「伝統を守るか、自由に拡張するか」という葛藤そのものでした。
一方、ギタリストのパット・メセニーは70年代後半から独自の道を切り開いてきました。叙情的なメロディ・センスと緻密なサウンド設計を武器に、ロックやワールド・ミュージック、電子音響までを取り込みながら、ポップに寄り過ぎることなくジャズの自由な表現を追求していきます。
1981年に発表されたアルバム『80/81』では、デューイ・レッドマン、チャーリー・ヘイデン、ジャック・ディジョネットらと共演。エレクトリックの文脈から離れ、アコースティックなインタープレイと即興性に挑戦する姿勢を明確に示しました。
ブランフォードやメセニーの動きは、80年代ジャズが一枚岩ではなかったこと、そして「どんな音を選び、何を手放すのか」という選択が求められていた時代であったことを物語っています。
原点への回帰とネオ・バップの兆し
1980年代に入ると、電化路線や商業主義に対する反動として、アコースティック回帰や伝統的な即興演奏の再評価が進み始めます。
その流れの中で、後に「ネオ・バップ」と呼ばれる一群の動きが、ニューヨークを中心に静かに台頭してきました。これは、50〜60年代のハード・バップをベースに、現代的なテクニックや新しい解釈を加えたスタイルでした。
たとえば、デイヴ・ホランドが率いたアコースティック・カルテットは、マイルス譲りの自由なアプローチを残しつつも、緊張感あるアンサンブルとインタープレイに重点を置く演奏を展開。その音楽は、電化路線とはまた違う方向で、ジャズの深みを追求していました。
ブランフォード・マルサリスも、80年代中盤以降にはコルトレーン的な語法をさらに追求し、アコースティックな表現へと明確に舵を切っていきます。
ウィントン・マルサリスの登場と価値の再定義
そうした中で登場したのが、ウィントン・マルサリスでした。1981年、アート・ブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズの一員として注目を集め、1982年にはコロムビア・レーベルからソロ・デビュー。まだ20歳ながら、クラシックとジャズ両方で高い評価を得る天才トランぺッターでした。
彼の演奏は、50年代ハード・バップの精神を現代に復活させるような端正さと構造美を持ち、クロスオーヴァーに傾きすぎていたジャズ界に新しい基準をもたらします。
評論家スタンリー・クラウチや作家アルバート・マレーの思想的なバックアップもあり、ウィントンは単なる凄腕ミュージシャンではなく、ジャズ文化そのものを再定義する存在となっていきました。
彼の登場は、ジャズが「新しさ」だけでなく「正統性」をも重視する方向へと舵を切る、80年代ジャズ史の大きな転換点だったのです。
おわりに
振り返ってみれば、1980年代初頭のジャズは、次に進むための時間だったのかもしれません。
クロスオーヴァーの熱気を引き継ぎつつ、伝統への回帰や新たな解釈が模索され、ブランフォードやメセニー、ホランドらがそれぞれの方法で、ジャズの現在地を問い続けていました。
そしてウィントン・マルサリスという決定的な存在が現れたことで、ジャズは再びひとつの軸を取り戻します。
この時代の一つひとつの選択と葛藤が、90年代以降のジャズの多様な地図を描くための伏線になっていたことは、今だからこそ見えてくる真実かもしれませんね。