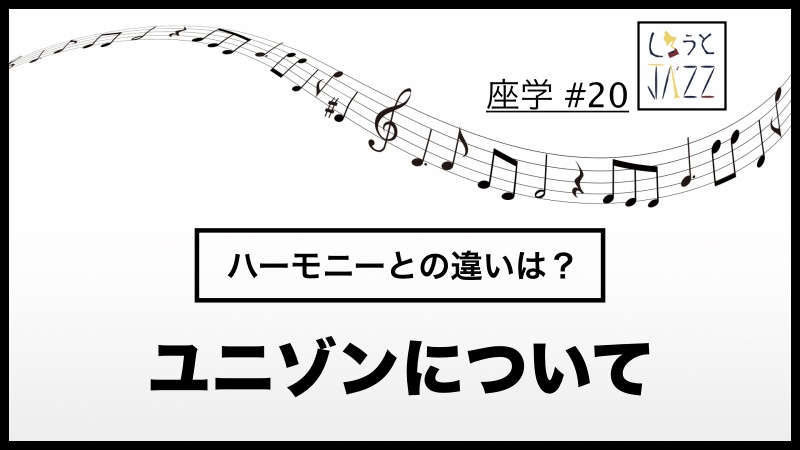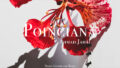どうも、ズワイガニです。
同じタイミングで発声した際に「ハモった」とかって言う時があるんですけど、この表現にちょっと違和感があるんですよね。
同じタイミングで同じように発声したらそれは「ユニゾン」じゃん。って思うからです。じゃあ「ユニゾった」って言えば満足か?っていう話なんですけど、そんなことが言いたいんじゃありません。
私が言いたいのは、「ユニゾンってもんもあるんやで」ということなんですよ!
はい、長々すみません(笑)
ということで、今回は「ユニゾン」について解説します。よろしくどうぞ。
ユニゾンとは?
ユニゾンとは、音楽において複数の楽器や声が同じ音程で同時に演奏・歌唱することを指します。
語源はラテン語の「unisonus(単一の音)」に由来し、日本語では「斉唱」「同音奏」と訳されることもあります。
ユニゾンの特徴
ユニゾンは、楽曲において強い一体感や力強さを生み出す手法のひとつです。同じ旋律を複数のパートが同時に奏でることで、サウンドが厚みを増し、統一感が生まれます。
また、ユニゾンを意図的に使うことで、楽曲の中で特定のフレーズを際立たせる効果も期待できます。
ユニゾンとハーモニーの違い
ここで冒頭の話にニアミスしますが、ユニゾンとハーモニー(和音)はしばしば混同されがちなんです。しかし、明確な違いがあります。
- ユニゾン:同じ音程で演奏・歌唱する。
- ハーモニー:異なる音程を同時に演奏・歌唱し、和音を形成する。
例えば、コーラス・グループが全員で同じメロディを歌うとユニゾンになりますが、異なるパートがそれぞれ異なる音程を担当するとハーモニーとなります。
ユニゾンの音楽的な役割
ユニゾンは、さまざまなジャンルの音楽で効果的な役割を果たします。
クラシック音楽
クラシック音楽では、オーケストラの序盤やクライマックスでユニゾンが用いられることが多く、特に金管楽器や弦楽器が同じメロディを演奏することで壮大な印象を与えます。
例えば、ベートーヴェンの『交響曲第5番「運命」』、第1楽章の冒頭のあの有名な「ジャジャジャジャーン!」のモチーフは、弦楽器・管楽器がユニゾンで演奏し、強烈な印象を与えています。
ジャズ
ジャズでは、ホーン・セクションやピアノのオクターブ奏法としてユニゾンが活用されます。マイルス・デイヴィスの『So What』やジョン・コルトレーンの『Giant Steps』にも見られるように、ユニゾンはジャズのアンサンブルを際立たせる重要な要素になります。
また、チャーリー・パーカーとディジー・ガレスピーの『Salt Peanuts』では、テーマ部分の高速なユニゾンが、ビバップのエネルギーを存分に発揮しています。
ロック・ポップス
ロックやポップスでは、ギター・リフやボーカル・ラインにユニゾンが取り入れられることがあります。
例えば、クイーンの『Bohemian Rhapsody』では、一部のセクションでユニゾンが用いられていて、楽曲のダイナミクスを強調しています。
邦楽・合唱
日本の歌謡曲や合唱曲でもユニゾンは頻繁に登場します。特に合唱曲では、冒頭や終盤で全員がユニゾンで歌うことで、楽曲のテーマを強く印象づけることができます。
例えば、合唱曲の『COSMOS』では、冒頭でのユニゾンが、歌詞の壮大さを表現していて、のちのハーモニー部分とのコントラストを生み出しています。
ユニゾンの応用
ユニゾンは単純に同じ音程を奏でるだけではありません。ユニゾンの表現方法は様々で、それによって楽曲の幅を広げることができます。
- オクターブ・ユニゾン:1オクターブ違いで同じ旋律を演奏する(例:男性ボーカルと女性ボーカルが1オクターブ差で歌う)
- リズミック・ユニゾン:異なる楽器が同じリズムでフレーズを奏でる(例:ベースとギターのリフが一致する)
- フェイク・ユニゾン:細かな音の装飾を加えながらも基本的な旋律を揃える(例:ジャズの即興演奏)
おわりに
ユニゾンは、楽曲において一体感を高める役割を持っているので、ジャンルを問わず幅広く活用されています。
単なる同音奏にとどまらず、オクターブ・ユニゾンやリズミック・ユニゾンなど、多様なアプローチによって音楽の表現力を豊かにすることができます。
こういったユニゾンの使われ方にも注目して聴いてみると面白いかもしれません!